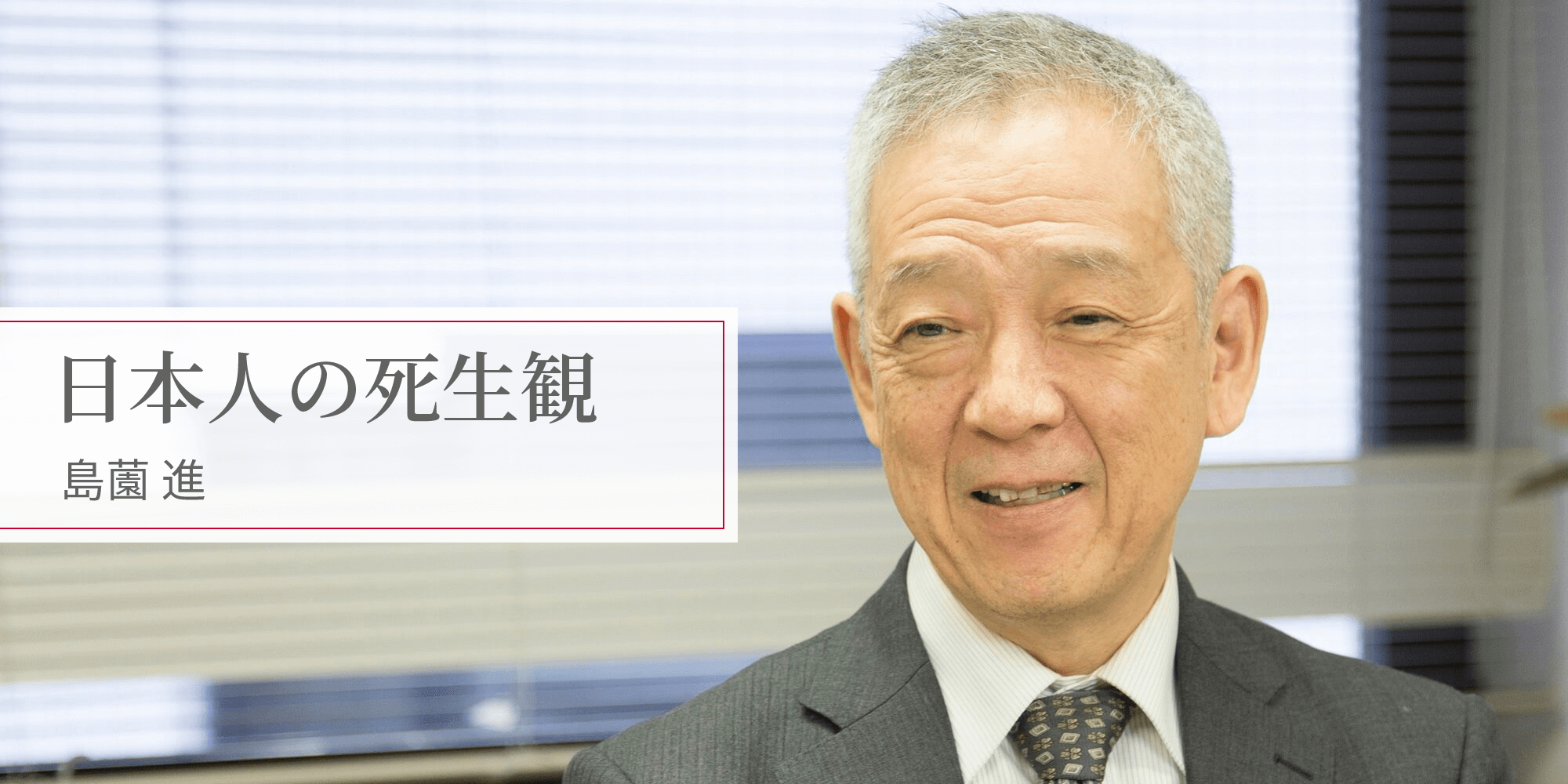――現代人は、私自身も含めて、死後の世界をそのまま信じるのは中々できないように思うのですが、そうすると生きている限り、死の不安から逃れるのは難しそうですね。
岸本英夫という人は、死後の世界というものが信じられなくなってしまった現代人が、どういうふうにして死を超えたものをイメージし、自分がそれにつながっている感覚というか、それに命を託すことができるようになるかを問いました。禅なんかもそうですけど、今この瞬間に集中しきることができれば、死の恐怖なんていうものはない。そこに、永遠のものにつながっている瞬間があるといえます。
こういうのはいろいろな武道や茶道、華道なんかにもありますね。「道」を歩いていけば永遠に通じるんだという考え方。そして、日々の営みは何でも「道」になる。それは私たちには確かに納得しやすい。たとえば、ピアノを演奏している人は、その演奏中はすべてを忘れてその曲の中に入り込んでいるわけですよね。その間は、これから死んでいくとか、死んで無になるとかいうようなことを超えた、永遠のものに通じる境地だと言ってもいい。

――それは、自分という主体と客体の区別がなくなるみたいな感じですか。
そうですね。禅はもちろんですけど、音楽にもそういうところがあると思います。聴覚的な世界。視覚は見るものと見られるものを分ける傾向が強いんですけど、聴覚というのはこっちから聞くというよりも聞こえてくるものなので、主客の境があいまいというか。これは西田幾多郎とか上田閑照先生などが言っている話ですけど、ボーンと鐘が鳴っているというのは、私が鐘の音を聞いているというより、鐘の音が鳴っているということがまずあるのであって、その経験の中では私とか鐘とかいうものはない。そういうふうな捉え方をしています。主と客を分けない、主客未分の世界。私なんかは字を書くのが下手ですが、本当に見事に字を書く人は、文字の世界に入り込んでいると感じます。
――没入してる感じですよね。
無為自然という言葉がありますけど、自分から何かをしようとするのではない。世界の中に溶け込んで、そこで自分らしさがおのずから分かるというふうな境地ですね。
――自己というものがあるからそれが消滅する死が怖いのであって、自己が世界とひとつになれば死を恐れる心もない。
あるいは、そういう心にとらわれる必要もない。自己にこだわることで生じる悩みから自由になる。それが自由自在な生き方であり、それこそが宗教の目指すものだ。そういう考え方は仏教だけじゃなくて道教にもあるし、儒教なんかにもあるかもしれない。「己の欲する所に従って矩(のり)をこえず」みたいな。
――実践できるかどうかは別として、理屈としては受け入れられる感じがします。理屈としては分かります。
ですので、ヨガをやるとか、気功をやるとかっていうのも、単に美容や健康のためという人も多いと思うんですけど、どこかで、とらわれからの解放、心の自由を得るためでもあると思うんです。そしてそれは、宗教的なものに通じている。