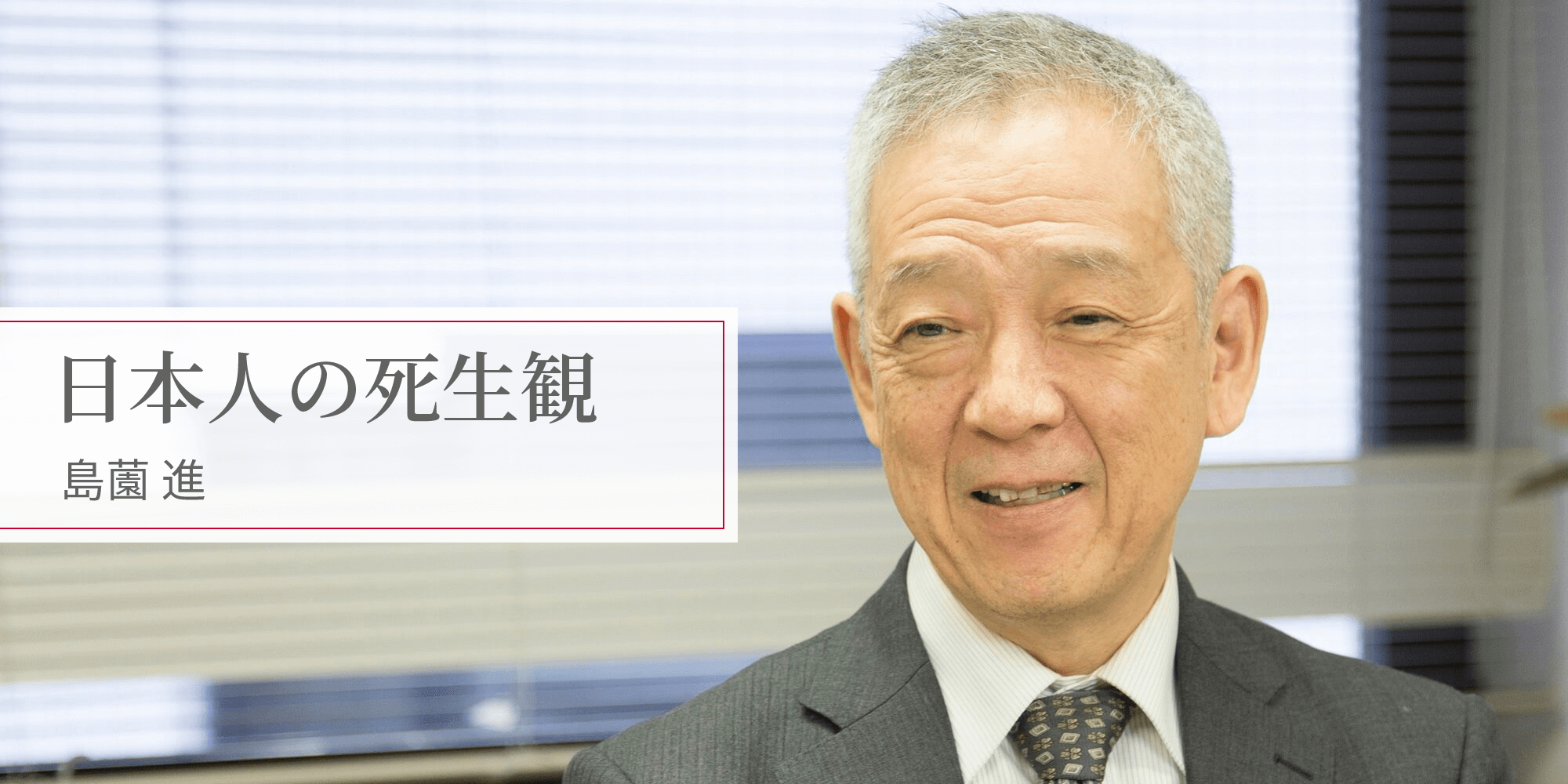――自殺という行為そのものは江戸時代からあったけど、明治の終わりに藤村操が「生きている意味がわからない」という理由で、初めて自殺をした。初めてと言っていいかどうかわからないですけど、「実存の悩み」みたいなものが出てきたということですね。
そのときに「煩悶(はんもん)」という言葉が広まったんですけど。これは生きている意味が分からない、あるいは、これまで皆が価値あると思っていたものが納得できない。その苦しみ、意味が見いだせない絶望。そのことを理由として死ぬみたいな。

「何のために生きるのか」と自分自身を問い詰めていって、宗教に行くこともできない。かといって、この世で世間並みにチャラチャラと適応していくことは潔しとしない。漱石の主人公は大体そんな感じですよね。漱石は「神経衰弱」という言葉を使っていますけど。悩む人間こそ現代の問題を正面から受け止めているんだ、それで宗教にも行けないなら死という選択しかないじゃないかと。
――江戸時代であれば考える必要もないことで悩むようになってしまった。
それは一般の庶民というより、官僚になるような旧制高校のエリートたち。彼らが哲学、文学、芸術なんかにうつつを抜かして、現実の世界をばかにしている。でも、こういう人こそ、本当は社会のリーダーになるべき存在なんだと。これを教養主義と言うんですけど、そういうニュアンスを伴った死の問い方。
現代社会ではそれがみんなのものになっているように思います。誰もが自分の死について、自分なりの答えを出さないといけない。これは責められているというか、今までみんながやってきたようにしていけばいいんだとは思えなくなった。そういうふうなことがいえると思います。
――誰もが、自分なりの死に方を見つけなければと感じている。
そういうことですね。
われわれは今、「グリーフケア研究所」で人材養成講座というのをやっています。これは水曜日の夜と土曜日にクラスを持っていて、一般社会人が対象です。参加している人の平均年齢は40代後半くらい。女性が多いんですけど、看護師さんから、いろいろなケア関係の仕事をしている人、主婦もいるし、メーカーの人もいるし、僧侶も医師もいます。こういう人たちは社会生活を経て、子育てをしたり、人生経験を積んで、あらためて生きている意味、死を自分なりにどう迎えるのか、こういうことを問うようになっています。 それはある意味では非常に自然ですよね。かつては教養という形で学んでいたこと、哲学とか宗教、芸術で問われているようなことを、人生経験を積んだ後にあらためて自分なりに考えてみたいと。
現代の社会で死生観が問われている背景にはそういうものがあって、漱石なんかの時代からは少し変わったと思います。少数のエリートが問うていた、ちょっと頭でっかちの死生観から、人生の悩みを経験し、親しい人が死んでいくのを見、自分も死に直面するような経験をしながら、あらためて生きている意味を問い直す。あるいは、人と共にある生き方を問い直す。そこにやっぱり哲学とか宗教、文学というものが必要だと感じ、そういうものに接したい、学びたいと思う人が増えている。
――そこには、そもそも今までは誰もが無条件に信じていた集団だったり宗教だったりというものが、そのままでは信じられなくなってきたというのがあるということでしょうか。
それは大きいでしょうね。
――それでもやはり、哲学や宗教や文学から、自分なりの死生観に結び付くものを見つけたい、学びたい、という流れが出てきているわけですね。
そうだと思います。