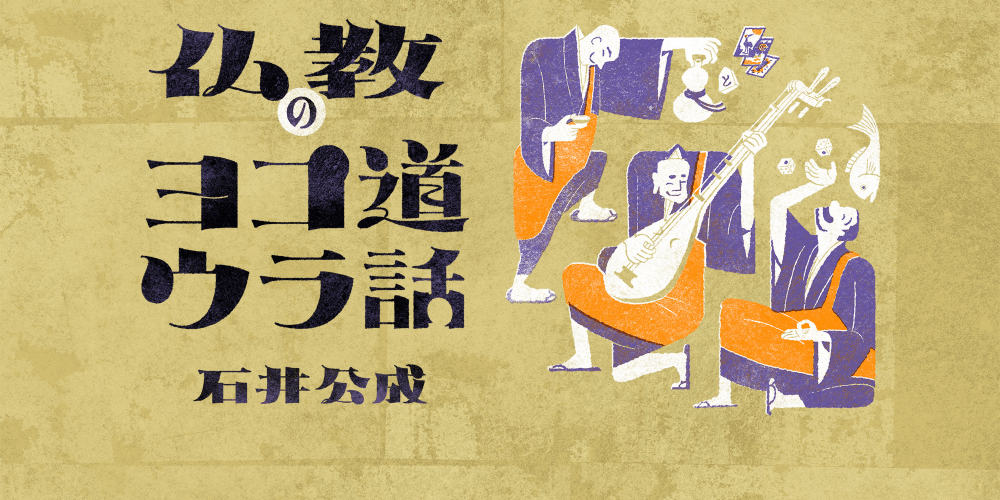この連載の記事
1. 僧侶の恋歌
インドでは、何らかの苦行をともなう修行生活をブラフマチャリヤと呼んでおり、この語は狭い意味では性に関して禁欲を守ることを意味します。ヒンドゥー教徒であったガンジーが、まだ36~37歳の男盛りの頃、妻に自分は「ブラフマチャリヤを保つことにする」と宣言し、以後守りとおしたのは、まさにその意味でした。古代に誕生した仏教も、
2. 仏教文献の誤写・誤植と文字作り
トイビト編集部
写経と聞くと、国宝の平家納経が示すように、一字一字に注意を払って正確に、しかも見事な筆跡で書かれているものと思いがちです。確かに、経典は慎重に書写されるのが通例ですが、学習のために経典の要所を抜き書きしておく場合とか、さほど尊敬されていない学僧の大部の注釈などは、雑に間違いだらけで筆写されることも多いのです。
3. 日本の清酒とコピーライターの元祖?
酒屋といえば、現代では酒を売っている店を意味しますが、古代には酒を造る建物のことを酒屋と呼んでいました。奈良時代初期に編纂された『播磨国風土記』では、「酒殿を造りし処(ところ)を、即ち酒屋の村と号(なづ)け」たと記しています。そうした酒屋は、実は大きな寺院にも置かれていました。
4. 琵琶を頭の後ろに回して弾く天女
楽器を曲芸のようなやり方で演奏することを、曲弾きと呼びます。曲弾きは、世界諸国で様々な例が見られますが、ギターを背中に回して弾くと言えば、ロック好きの人は、ジミヘンの愛称で知られるジミ・ヘンドリックス(1942-1970)を思い浮かべることでしょう。
5. サウナの功徳を説いたお経
第三回目の記事で寺の「酒屋」について触れましたので、今回は「湯屋」にしましょう。むろん、共同浴場は仏教が起源だという話です。なんでもかんでも仏教由来にするなと怒られそうですが、事実なのですから仕方ありません。
6. 伝染病と仏教
下火になってきたとはいえ、コロナ禍が続いていますので、伝染病と仏教の関係について述べておきましょう。実は、釈尊の時代にも伝染病が流行したことがありました。釈尊がマガダ国の都に滞在していた際、隣国で疫病が広まり、釈尊が出かけていってそれを終息させたとする伝承が、複数の経典に説かれています。
7. 乳の仏教学
前回は伝染病と薬の話であって、維摩詰(ゆいまきつ)が病気となった姿を示す『維摩経』にも触れました。その『維摩経』では、釈尊がちょっとした病気になった際、弟子の阿難が釈尊に命じられ、牛乳を布施してもらいに出かけたところ、皮肉屋の維摩詰に出会います。
8. マリア観音と鬼子母神
前回は、釈尊の母の説話との類似ということで、幼子イエスを膝にかかえる聖母マリアの絵に触れました。現代の日本人がこうしたマリア像に似ている東洋の作品と言われて思い浮かべるのは、狩野芳崖(1828-1888)の名高い「悲母観音」でしょう。しかし、観音は「大悲観世音」と称されて信仰されてきたものの、「悲母観音」「悲母観世音
9. 禅僧の望郷詩
前回は、福建で焼かれた白磁のマリア観音像が日本にもたらされたという話でした。むろん、白磁の像が自力で泳いでくるはずもなく、商人たちの船で運ばれてきたのです。当時、陶磁器は交易の重要な品目でした。
10. 和尚と小僧
前回は、禅僧と言うと「喝!」と叱り飛ばすようなイメージがあるものの、意外にも望郷の念にかられる面もある例を取り上げました。ただ、一般の人が禅僧と聞いて思い浮かべるのは、頓知ばなしでおなじみの一休さんかもしれません。
11. 修行としての便所掃除
前回は「和尚と小僧」の笑話の代表として、一休さん話をとりあげ、モデルとなった一休宗純禅師(1394-1481)にも触れました。その一休は、大応国師(1235-1309)が宋で臨済禅を学んで帰国した後、京都に禅寺として建立した妙勝寺が戦火で失われたこと歎き、寺を復興して晩年はそこで過ごしました。それが一休寺という通称で
12. 「こころの時代」はアメリカ由来
前回書いた便所掃除については、「便器を磨くことは、心を磨くことだ」といった教訓が語られることもあるようです。それが日本の、とりわけ仏教の伝統だとされるわけですが、心重視という点で気になるのは、一時期、盛んに語られていた「こころの時代」という言葉です。
13. Zenという表記はいかにして生まれたか
前回は、「こころの時代」はアメリカ由来だという話でした。仏教関連でアメリカ由来であるものは、実はほかにも少なくありません。その代表例は、Zen という表記でしょう。
14. 肩から炎、足もとからジェット水流を放つ仏
前回は、Zenという表記であったからこそ、東洋の神秘を感じさせ、人気になったという話でした。ただ、皮肉なことに、禅宗は神秘的なことを嫌うのです。
15. 地獄に落ちたお釈迦様
前回は、釈尊が肩から炎、足もとからジェット水流を放って空に浮かぶ話でした。ジェット水流は用いないにしても、釈尊が神通力で空を飛んだとする記述はかなり見られますが、今回は釈尊が墜ちたとする経典をとりあげます。しかも、よりによって地獄落ちしたという話です。
16. なぜ鬼は虎皮のパンツを履くのか
前回はお釈迦様が地獄に落ちる話でした。地獄と言えば、鬼がいて悪いことをした亡者たちを苦しめるところであって、その鬼については、虎皮の腰巻や幅広の褌(ふんどし)をしているというのが今日のイメージです。童謡やドリフターズの替え歌では、鬼は虎皮のパンツを履いていることになってますね。
17. ペット供養は唐代からあった
前回は地獄の鬼の話でした。仏教では、人が死んだ後に生まれる世界のうち、地獄・餓鬼・畜生のあり方を「三悪趣」、つまり三つの悪い世界と呼んでいました。畜生といってもことらさらにおとしめた意味ではなく、要するに動物のことです。
18. 僧侶による戦死の礼賛と桜の花
前回は、敦煌写本に見られる動物の追善供養のための願文マニュアルには、犬・牛・馬など様々な動物のための願文例はあるものの、猫に対する願文が無いという話でした。実は、もう一つ欠けているものがあります。それは戦死者のための願文です。
19. 漢訳仏典の音写語が日本語になるまで
トイビト編集部
前回は、仏の軍勢と地獄の戦いということで、閻魔王に触れました。インドでは死後の世界の王を「ヤマ・ラージャ」と呼んでおり、「ヤマ」はその王の名であって、「ラージャ」は王という意味です。つまり、閻魔王の「閻魔」は、「ヤマ」を音写したものだったのです。このため、「閻摩・閻磨・夜磨」など様々な表記がなされていました。