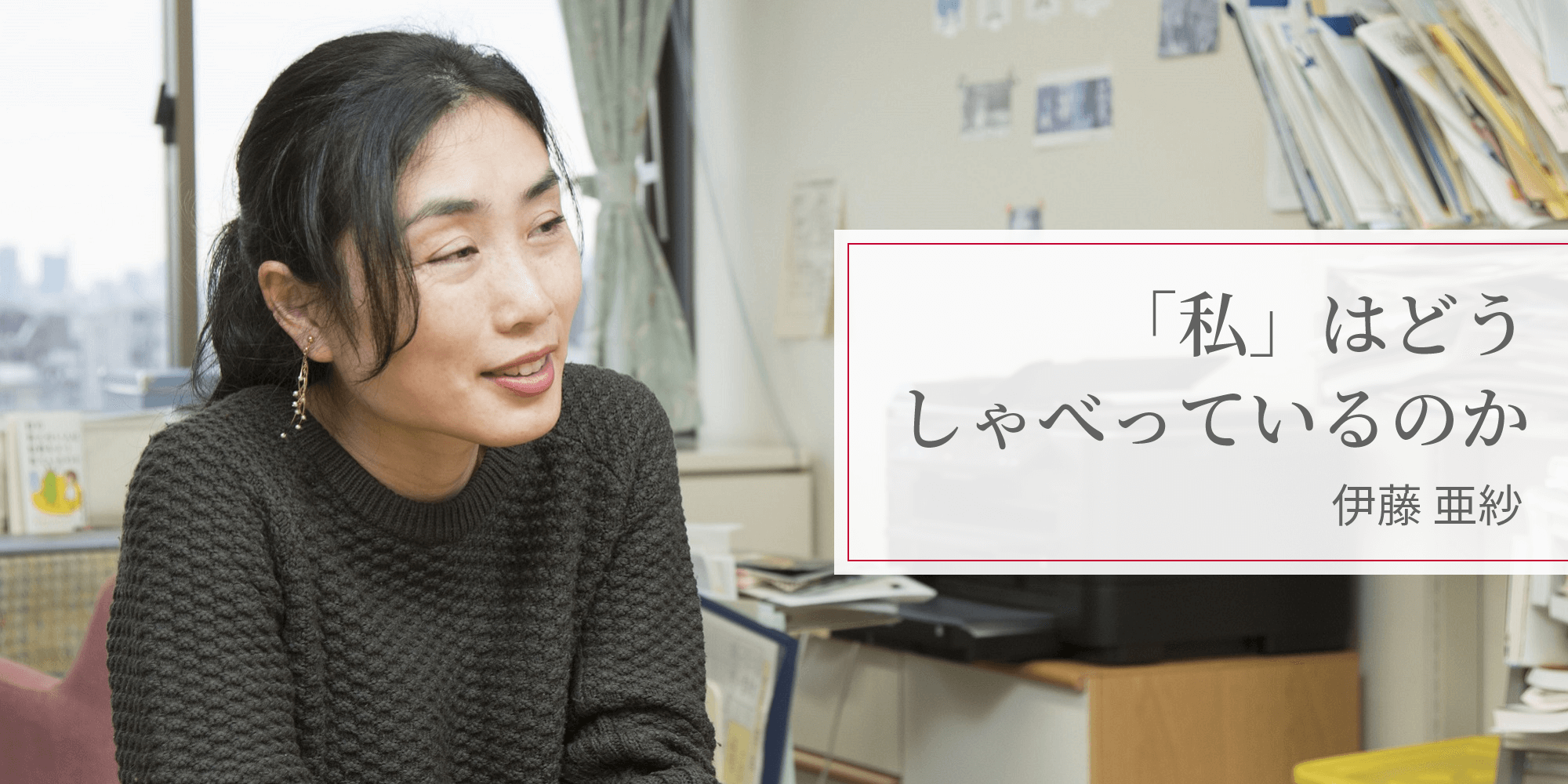――「キャラ」を演じるとしゃべりやすいっていうのは感覚的にはなんとなくわかるんですけど、しゃべる内容は当然自分がしゃべりたいことをしゃべるわけじゃないですか。別に映画やアニメのキャラの決まったセリフをまねするわけじゃないのに、それで吃音が出なくなるっていうのは不思議ですね。
さっき不確定要素が大きいとどもりやすいってお話しましたけど、実はその逆もあって、不確定要素がゼロ、つまり、やんなきゃいけないミッションがはっきりしていて、それをその通りに遂行するっていうのもつらいんですよ。
――国語の授業の音読で吃音が出る方はそのタイプなわけですね。
そうですね。なにか前例はほしいけど完全には決められてなくて、ちょうどいいくらいの自由度があるっていのうがラクなんです。
――ちょっと思ったんですけど、しゃべりやすくするためにあるキャラを演じているということは、そうではない自分、「本当の自分」というものがあるわけですよね。でもその「本当の自分」というのもある意味パターンなんじゃないのかなって。吃音のあるなしにかかわらず、誰かと話すときは常にその場における「私」を演じていると思うんです、意識的であれ無意識であれ。
微妙なところですよね。演じるっていうのはもしかしたら、両足をそれぞれ違う所に置いているというのが重要なのかもしれないです。だから確かに、私とか自分とか言うときにも演技性はあるんですけど、それが自然なもの、当たり前なものになっちゃうと吃音的にはその効力を発揮しない。着脱可能な状態というか、それと一体化しすぎてなくて、使いこなしてる感みたいなのが自由度を生むような気がしますね。
――他のキャラもあるんだけど、今はこのキャラを使ってるみたいな。
そうですね。ただ実際はしゃべりやすいキャラにすごく乗っかっちゃって、それが症状になっていくことも多いんですけど。演じることが対処法として機能するのはやっぱり自分のほうに選択権があって、それを使ってるんだって思えるときですね。逆に自分が使われちゃうとそのキャラに乗っ取られて、それが症状になっていくんだと思います。

――『どもる体』のあとがきには先生ご自身も吃音があると書かれていましたが、今日ここまでお話しいただいた中でも、たとえば言い換えたりはされていますか。
言い換えてますね。言い換えは小さい頃から普通にしているので。
――まったく気づきませんでした。じゃあ、2倍のスピードで頭を使ってるってことですよね。
でも、言い換えもパターン化してるので。「これでいけるかな」みたいなのが、ケータイの予測変換みたいに出てくる感じですね。
――たとえば「たまご」は言いづらいから毎回「エッグ」と言い換えてたとしますよね。その場合でも最初はやっぱり「たまご」が出てくるんですか。最初から「エッグ」にはならない?
それがいつも不思議なんですけど、その言葉が自分の語彙から消えるわけじゃないんですよね。だから、言い換えのリストみたいなものがあるわけじゃなくて、準備したときの感覚で判断してるような気がします。
――なるほど。人がどういうふうにしゃべってるのかって分からないものですね、当たり前ですけど。
でも、何でもそうだと思いますよ。食べ方にしても、口の中で食べ物をどういうふうに移動させてるのかって、人それぞれ違うと思いますし。
――そう考えると、私たちが意識的にやってることって本当に少ししかないんだなと思います。
それが人間をすごく救っているんですよね。意識でぜんぶ動かしていたら本当に大変ですよ。中途障害の人って、健常者のときには意識しないでできていたことを意識的にやらなきゃいけなくなるので、そこが大変なんです。
たとえば足を切断して義足をはめると、それまで意識したこともないようなことを考えながらやらないといけない。ベッドからただ立ち上がるだけでも、まずここに重心をもってきて、このタイミングで力を入れてって、意識してやるようになる。それがすごく大変で、毎日すごく疲れちゃうそうです。だから、意識せずにできるっていうのはすごいことなんだと思います。
――それがそのまましゃべることにも言えるわけですよね。普段自分がどうしゃべってるのかって、考えちゃうとわかんなくなりますね。まさに今、私がこうしゃべってるのもどうやってるんだって。
本当に、誰がしゃべってるのか分かんなくなりますよね。
言葉自体の働き
――今日ちょっとお聞きしようと思ってきたのが、しゃべることと書くことの関係性ってどうなってるんだろうってことなんですね。作家がよく、作中の人物が勝手に動き出すみたいなことを言うじゃないですか。個人的には「本当?」って思うんですけど、でもしゃべっているうちに言葉が出てくるみたいなことは私もあるので、もしかするとそれに近い感じなのかって。どう思われますか。
言葉自体の動きというのは私もすごくある気がしています。なんらかの言葉を置いたことによって勝手に連想が働いてしまったりとか。書くという話につながるかどうか分からないんですけど、最近、「話が飛ぶ」ということにすごく興味があるんです。
話が飛ぶのって、その人の中での連想と、今、会話をしてるという社会的な状況とがぱっと乖離しちゃうってことですよね。だから、聞いてるほうからすると話が飛んでるように思うけど、本人としては、あるいは体としてはつながっている。
言葉ってそういう風に体の生理にも関わるし、もちろん社会的なツールでもあるので、言葉自体が次の言葉を呼び込んだり、自分の思考が言葉に引っ張られたりということはすごくありますよね。それは多分、しゃべるのも書くのも差はないのかなっていう気はします。
――なるほど。
でも人によっては、たとえばメールで持つ印象と実際にお会いしたときの印象がまったく一致しない人っていますよね。
――いますね。
不思議なんですけど、書いたものは推敲できるので、つくれるということかもしれませんね。
――言語を獲得する以前には物事を認識すること自体が難しいってことを考えると、「私」とか「自分」っていうのも結局は言葉によって構成されているわけですよね。そうなると、言葉を離れた私ってどんな存在なんだろうって考えることがあります。
「言葉を離れた私」も興味深いですけど、同じくらい、「私を離れた言葉」も面白いと思うんですね。最近、認知症の方の調査を始めたんですけど、その両極なんですよ。「私」の方に引っ張られる方もいれば、「私」のない言葉だけがばーっと出てくる方もいらっしゃいます。

よくあるパターンですけど、どんな話をしていても最後は同じ話になる方は私の方に寄っていくタイプですね。あれ、気付いたらまたその話、みたいな。するっと回収していく。それはそれですごいなと思うんですけど。
一方で、すごく即興性を感じることもあるんです。この辺はまだ研究し始めたばかりなので確定的には言えないんですけど、相手の発した言葉に反応しているという側面があると思うんですよね。誰かが言ったことに対してぱっとダジャレを言ったりとか。論理的な会話は難しくても、そういうのは普通にできる方もいます。
――それは興味深いですね。
確かに言葉が私をつくっているんですけど、同時に、私という輪郭が曖昧になったときの言葉の出方はけっこう多様なので、そこはちょっと考えていきたいなって思っているところです。
――言葉が言葉に反応して出てくるという感じですか。
そうですね。言葉が言葉を引っ張ってくるっていうか、私の検閲なしに言葉が出てくるというか。
――そういえば何でもだじゃれにできる人っていますよね。おやじギャグだってバカにされますけど、あれはあれですごいと思うんですよ。
そうなんですよね。
――ただ、おやじギャグは確かに、「私」の検閲を通ってない感じがします。
周りの人はそれがイヤなんですよね。それでいらっとするんですけど、本人は言わないわけにいかないんですよ、多分。
――若いときなら言うのを思い止まっていたであろうギャグが、歳を取ると止まらなくなる感じは、最近よく分かります……。
「自分」の輪郭
――俗にいう「身心二元論」って、体があって、それとは異なる私がいるってことですよね。それが心なのか意識なのかは別としても、さっきお話したみたいに、言語を獲得していなければ「私」さえ認識できないのであれば、もういっそ私とは言語であると言っちゃってもいいのかなって。
うーん、難しいですね。社会的な意味での私もあれば、身体的な意味での私もあるので。言葉が私だって思う部分もありますけど、吃音的にはその場合の言葉って、単なる概念ではなく、自分の身体との関係で語られるものなんですよ。言いやすい言葉もあれば言いにくい言葉もあるので、身体運動としての側面がどうしても関わってくる。
にもかかわらず、社会的にはそれが共有されない。内面のドラマとしては間違いなくあるんだけれども、コミュニケーションのテーブルに乗っけることができないというのが、吃音の特殊で、もしかしたら苦しい部分かもしれないです。身体的な自己をそのまま出せなくて、言語的な部分しか共有されないっていう。
――ちょっと思ったんですけど、吃音のある方は、たとえば「私とは何か」って考えてそれについて書くのと、こうやって誰かと話すのとでは、言いにくい言葉がある場合には別の表現になるわけですよね。
そうですね。書いてるときは純粋な言語なので体は無視できるんです。書くのと話すのとでは、そこが一番の違いかもしれないですね。
――書くのは書けるんだけど、話そうとすると別の言葉になっちゃうとしたら、確かに自分を偽っている感じがするかもしれないですね。
でも、言語がすべてじゃないと思うんです。私、すごく好きなサークルがあって。「バンバンクラブ」っていう、視覚障害者のランニングサークルなんですけど。視覚障害者がランニングをするときって、輪っかにしたロープの両端を見える伴走者と見えない人が持ってシンクロしながら走るんです。で、そのロープがすごいんですよ。ただのロープなんですけど、やってみると3秒くらいで相手のことが好きになっちゃうんじゃないかというくらい、相手のことを生々しく感じるんです。
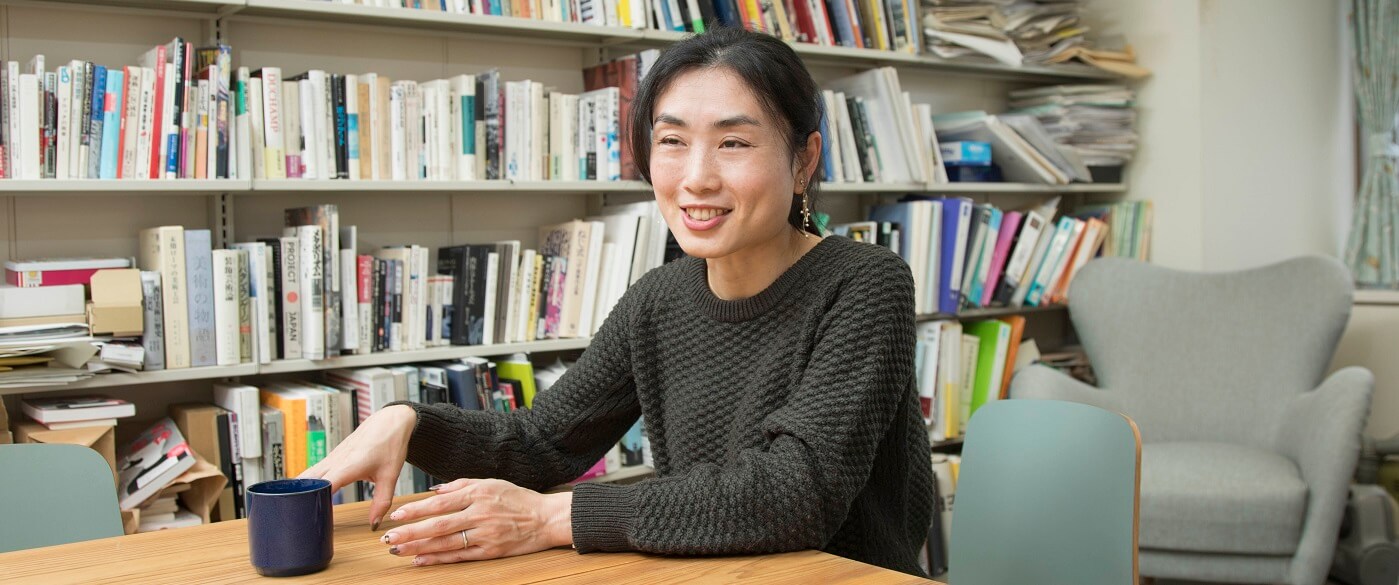
触覚的な情報ってすごいなって思うんですけど、何もしゃべらなくても、そのロープを通じていろんなことをやり取りできるんですよ。少し先に坂があったりすると、伴走者は見えるので「坂だ」って思うわけですよね。それで、ちょっと頑張ろうといった気合が、もう、すっと見えない人に伝わっちゃう。緊張とか、ちょっとした呼吸の変化とか、そういったことが全部、神経線維みたいに伝わりあうんです。そういうのもコミュニケーションなので、言葉によるコミュニケーションをもうちょっと相対化してもいいのかなっていう気はしますね。
――なるほど、面白いですね。
言語によるコミュニケーションは発信者側と受信者側を明確に分けるんですけど、最近「伝える」ってそうじゃないんじゃないかって思っているんです。片方が持っている情報をもう一方に伝達するっていうよりは、一緒につくっていくみたいな。そういう関係のほうがラクな場面が多いので。
――ロープでつながって走っている二人は正に一心同体というか、いうなれば一つの自己になっているような感じかもしれないですね。
そうだと思います。だからもう相手を信頼するしかないって感じで、それが、すごく気持ちいいんだと思うんですよね。自分を完全に相手に預けてしまうっていう。それこそ「降りる」っていう感じですよね。
――自分が自分じゃなくなる。いや、そこでまた「自分」って言っちゃうとややこしくなるのかな。
自分に対するこだわりって、どこから来るんですかね。
――それもすごく不思議ですよね。以前のインタビューでもご紹介したんですけど、禅僧の南直哉さんが本の中で、坐禅をしてると自我が溶解して、床が痛いとか襖がかゆいみたいな感覚になると書かれていました。体は物質なので境界線がはっきりしていて、ここまでが自分だって普通は思っちゃうんですけど、それとは異なる自己のあり方もあるのかなって。
体って、自分の輪郭を決めてるようでいて、実は自分を拡張するための一番のツールにもなるんだと思うんですよね、物理的だからこそ。
――物理的だからこそ?
私が障害の研究をしていて一番おもしろいのがそこなんです。障害があるっていうのは自分の体だけでは完結できないということなので、必然的に周りの人の力をうまく使うことになります。さっきのロープを使った伴走もそうですけど、そうやって、いろんなものを上手に呼び込んで、自分をネットワーク化していく。障害を持っているというのは、そうやって生きていくってことなんです。その柔軟さみたいなものがすごくおもしろいなって。
――それは新鮮な視点ですね!
さっきの伴走も、究極的には伴走者が消えるって言うんです。あまりに上手に伴走してくれると、伴走者が消えて道が見えるって。自分は見てないんだけれど、この人の視界が自分の中に入ってくる、みたいなことをおっしゃる方もいます。能力って、人のものをうまく使ったり、逆に自分の能力を貸したりとかが結構できるんですよね。その貸し借りみたいなものが、障害を通すことでよく見えてくるんです。
――今の世の中って他人に迷惑をかけるなとか、自分のことは自分でやれ、みたいなのがすごく強いじゃないですか。でもきっと、本当はそういうものじゃないですよね。
そう思い込んでるのは健常者だけかもしれないですよ。誰だって実際には、いろんなものを使って生きてるわけですからね。